インデックス型の商品は『多産多死の時代』を迎えています
2019年11月25日
こんにちは。
投資信託クリニック代表の カン・チュンド です。
アウターガイさんの記事からです。
【大和証券投資信託委託の「Mr.ETF」シリーズのうち計20本が上場廃止・繰上償還へ】
大和証券投資信託委託が運用する「Mr.ETF」シリーズのうち、
合計20本について繰上げ償還が決定したのだそう。
株式市場への上場が廃止となります。)
上記20本のうち、
多くがいわゆる業種別(セクター別)ETFです。
2008年に上場して以来、上記セクターETF群については
正直「売買高がほとんどない」状況が長らく続いたため、
遅すぎる決断だったと思います。
アウターガイさんは
繰上げ償還される業種別ETF(17本)プラス3本について、
丁寧に調べておられます。
最も大きいのは「ダイワ上場投信-東証電気機器株価指数」の26億円でしたが、残る19本はすべて10億円未満となっており、運用継続が難しい状況だと言えます。

ETFにしろ、
インデックスファンドにしろ、
純資産額があまりにも小さいと、
金融機関にとっては「信託報酬」(売上げ)がきわめて乏しくなり、
赤字を垂れ流すだけの金融商品になってしまいます。
モーニングスターの記事
【繰上償還の“実態”-注意すべき純資産額の水準は?】
を見ても、
10億円という水準が繰上償還の可能性が高まる一つの目安となる。
としっかり記されています。
(純資産額のことです!)
この『10億円という目安』については
しっかり頭の中に刻んでおきましょう。
また驚くべきは
2017年に公募投信で「293本」ものファンドが
繰上げ償還されたという事実でしょう。
(上記記事が伝えています・・)
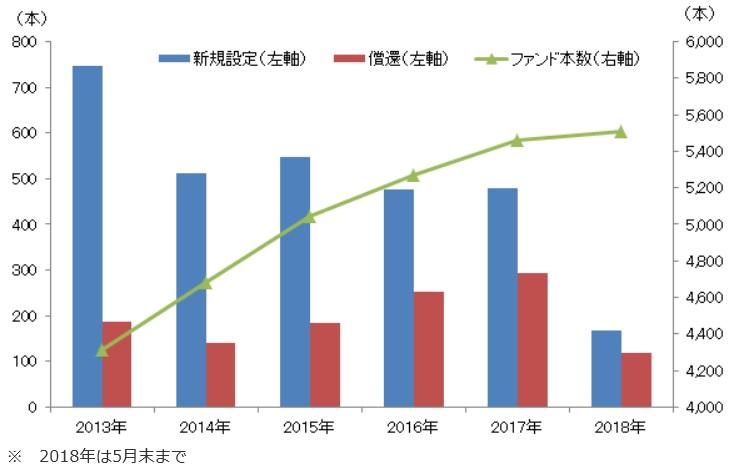
画像元:モーニングスター
「多産多死」の世界なのです。
しかしながら、
インデックス型の商品は今後とくに、
『少産多死』を目指さないといけないのかもしれません。
??
ちょっと考えてみましょう。
アクティブファンドと違い、
インデックスファンド(含むETF)は
特定の指数との連動を目指すことが
商品のそもそもの目的ですから、
そんなに『本数』は?
要らないのです。
たとえば
つみたてNISAを例に挙げてみましょう。
つみたてNISA対象ファンド内の、
MSCIコクサイ指数との連動を目指すインデックスファンド(つまり、先進国株式イ・ファンドのこと)をひとつ見ても、
首をかしげてみるべきなのです。
あるいは、
ひとつの運用会社内で、
2つも3つも、
MSCIコクサイ指数との連動を目指す『マザー・ファンド』が存在していて、
おまけにそれぞれの『マザーファンド』傘下で、
5つも6つも同じ先進国株式インデックスファンドが
ぶら下がっているとしたら、
「えっ、なんと非効率な、出鱈目な管理状況でしょう!」
と驚嘆するかもしれません。
意味のない「多死」を(結果として)招いているわけです。

わたしは今後、
ETF、インデックスファンドにおいて、
ファンドの統合、
ファンドの繰上げ償還等によって
一時的に「多死」が進むと考えます。
これは長い目で見れば、
需要と供給のバランスの観点からも良いことなのです。
(明らかにインデックス型商品の『数』は多すぎるわけですから)
「少産・多死」化が進めば、
1本あたりのインデックスファンドの
【平均・純資産額】も大きくなってきます。
そうすれば?
理に適った『けいぞくコストの低下』も
はじめて視野に入ってくることでしょう・・。
カテゴリ:インデックス投資全般


