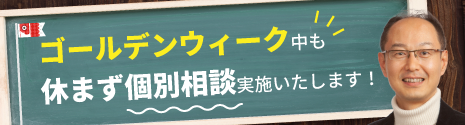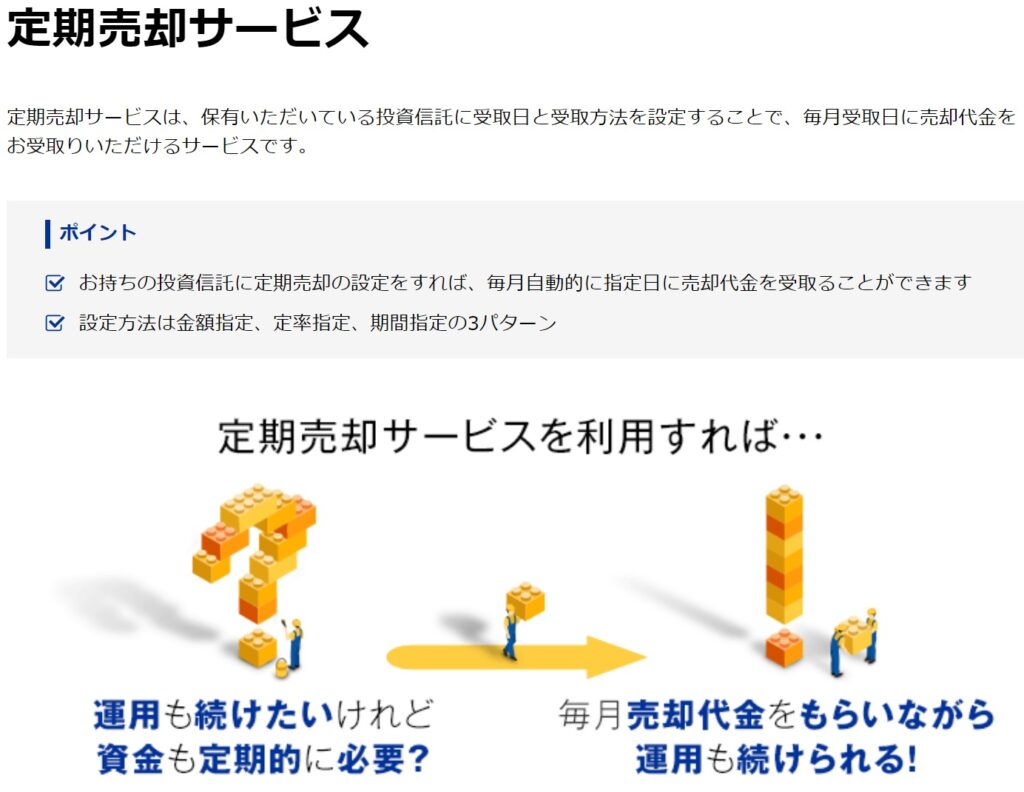『定額』取り崩しと『定率』取り崩しの本質的な違いについて【前編】
2025年4月18日
こんにちは。
投資信託クリニックの カン・チュンド です。
心のどこかで(何となく)、
『定率』取り崩しのほうがいいかな・・と思う心地はあっても、
それが理屈的に
より優れている管理方法であると(なかなか)実感しにくいものです。
なぜなら、
リタイア後の「資産管理」において、
毎年毎年ファンド価格が
どのようにアップダウンするか(= 毎年の「結果収益率」が何パーセントになるか?)は予め決まっていないためです。
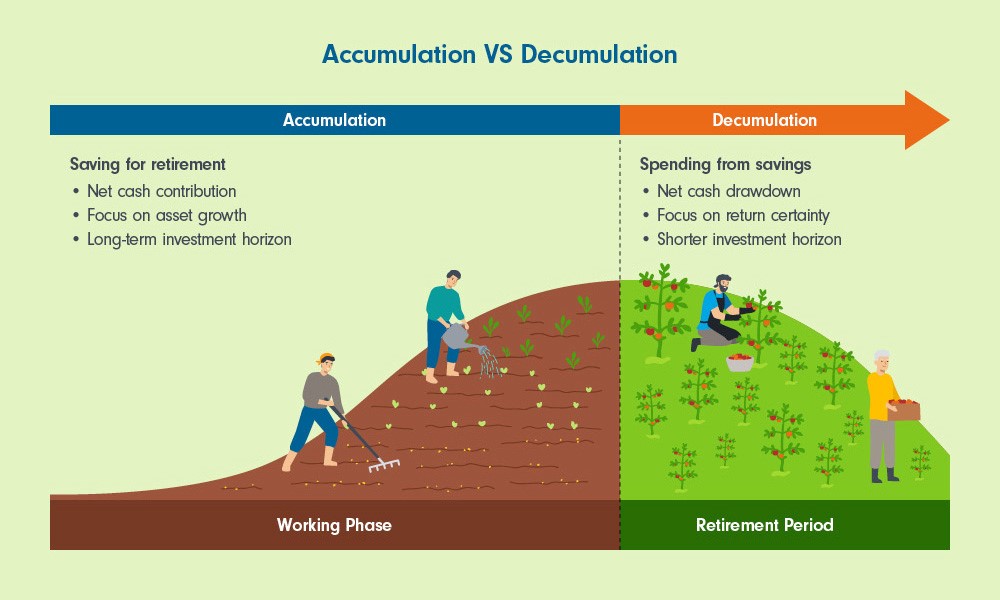
両者の比較においては、
具体的な『例』を挙げて、
シミュレーション比較してみたほうが分かりやすいのかもしれません。
そう思っていたら、
FPの頼藤 太希さんの記事を見つけました。
(NEWS PICKSに掲載の記事)
まずは、
大事な『前提』のところを整理しておきましょう。
実際は「毎年◯%で運用できる」という保証はありません。
運用成果を年単位で見れば、
大きく値上がりする年もあれば、
少ししか値上がりしない年もあるでしょう。
値下がりする年もあるはずです。
さらに、値上がりする年・値下がりする年がいつやってくるかでも、資産残高の推移が大きく変わってきます。
はい、その通りですね。
頼藤さんは記事内で
10年間、資産の取り崩しを行う中で、

ところが、です。
年率+4%のリターン(10年間)といっても、
実にいろいろなパターンがあるわけです。
単純に考えても、
パターン2)前半成績が悪くて、後半は良かった。とか。
ここからがいよいよ本題なのですが、
頼藤さんは『定額』取り崩しにおいて、
パターン2)前半成績が悪くて、後半は良かった【後半の収益率が高い場合】
の2パターンを、実際に提示されています。
それが下記図表です。
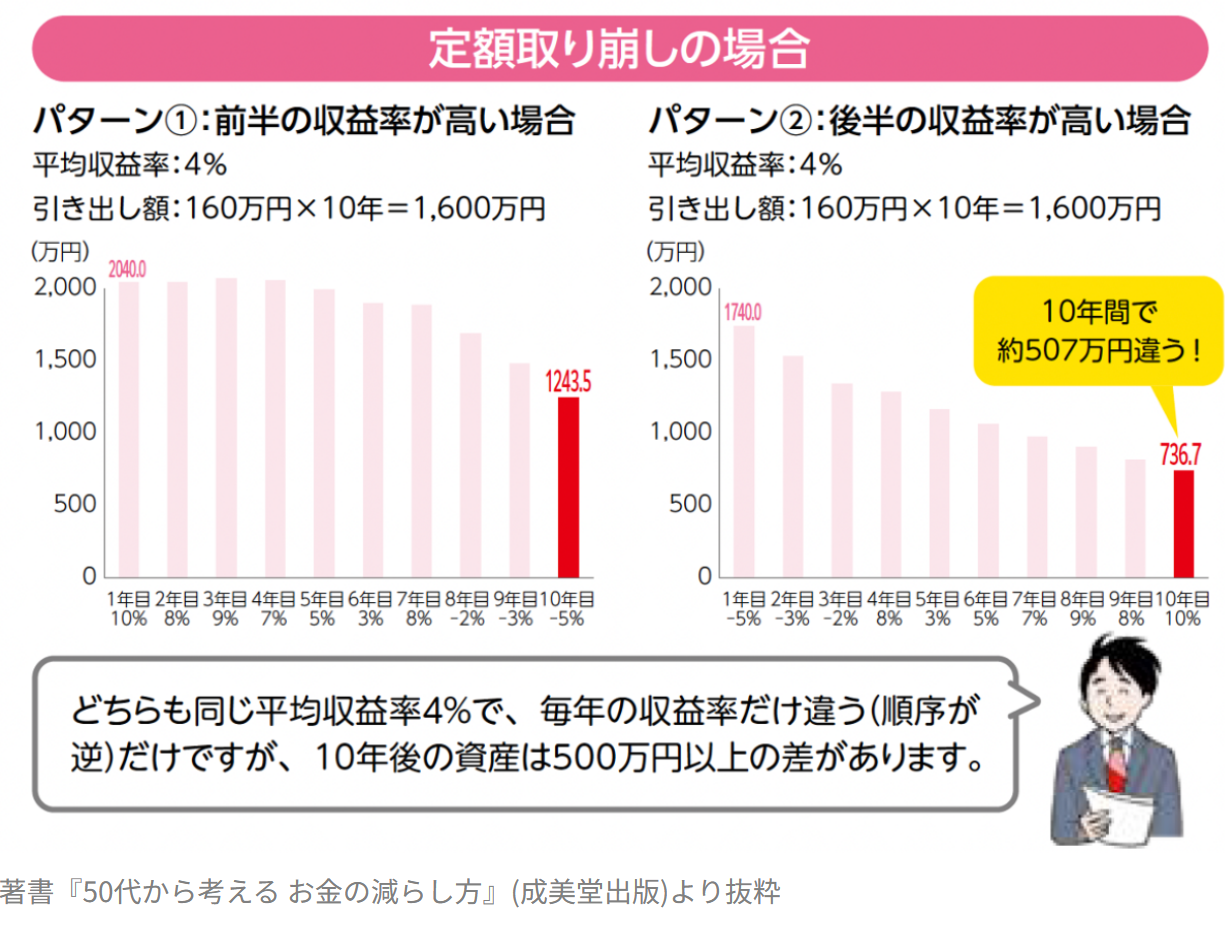
画像元)NEWS PICKS
『「資産を築く」よりも「資産を使う」方が断然難しいって話』
※1年目、2年目、3年目・・の下に記されている数字が、実際の各年の結果リターンです。
パターン1、パターン2とも、
毎年『160万円』(当初8%相当)ずつ取り崩すという「前提」です。
繰り返しですが
ポイントは、
〇 10年間の通算で見ると、
どちらのケースも「年率+4%の収益率」であった。
〇 そして、どちらのケースも、10年間での「トータルの引き出し額」は1600万円であった。という点です。

パターン1)
前半成績が良くて、後半は悪かった。
よりも、
パターン2)
前半成績が悪くて、後半は良かったケースのほうが、
資産の減少割合が大きくなっています。
言い方を換えれば、
『定額』取り崩しでは、
同じ「平均・結果収益率」(10年間)であっても、
毎年毎年どのような結果リターンの軌跡を描くのかで、資産の変動の仕方が大きく違ってくるということなのです。
後半に続く・・)
カテゴリ:リタイアメント・資産の取り崩し