カンさんはなぜ、安全:リスク資産 = 50:50を推奨するのですか?
2025年2月3日
こんにちは。
投資信託クリニックの カン・チュンド です。
安全:リスク資産 = 50:50を推奨される理由って何ですか?
これはYouTubeライブでも、
また、運用相談でもしばしば頂くご質問です。
まず結論を言いますと、
資産形成期(積立期)においては、
安全:リスク資産 = 50:50にこだわる必要はないと思っています。

もっと言えば、
安全:リスク資産という「骨太比率」を意識することさえ、あまり必要ないかもしれません。
※ただし、最低「月収の半年~1年程度」の『生活防衛資金』は手元に用意する必要はアリですよ。
30代、40代のあなたへ。
仕事があって収入があって、
リスクを負って、
どんどん投資への入金力を高めていく。
ここで頑張って資産形成しないで「いつ」するの? というイメージです。

わたしが推奨する
安全:リスク資産 = 50:50 は、
リタイアを控えた人、
リタイアを迎えた人へのおススメなのです。
仕事(定期収入)がなくなり、
資産活用期(取り崩し期)に入ろうとするあなたは、
公的年金を除いて、
自身の「総資産」を管理し、
計画的に取り崩し、生活を続ける必要があります。
最大のポイントは?
安全:リスク資産 = 50:50 とし、定期的なリ・バランスによって「50:50」を維持しながら、取り崩しをすることです。
この、
50:50を維持しながら、
の部分に対しての
「えっ、なんでなの?」という疑問ですよね。
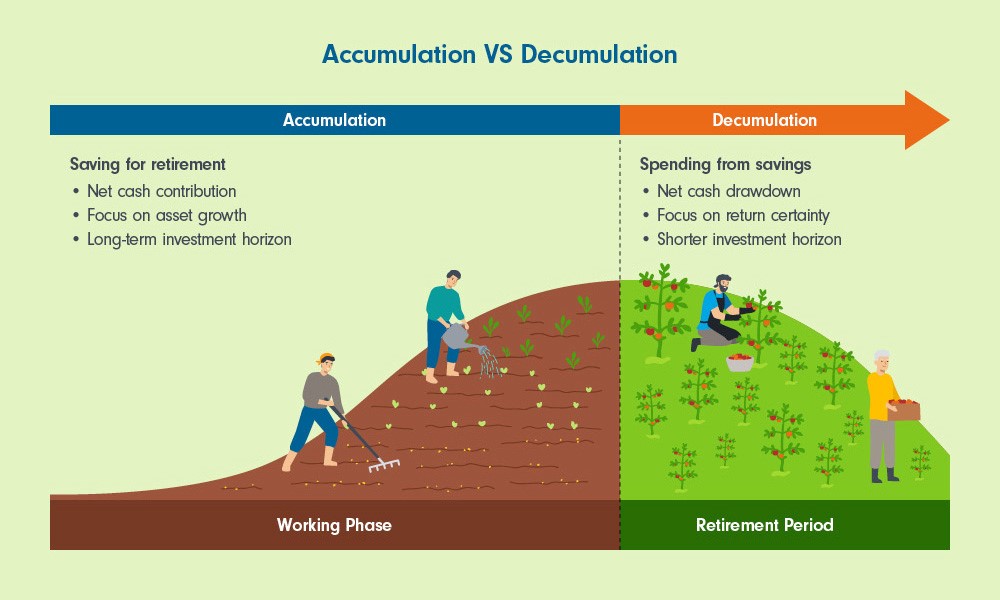
「答え」を言いますと、
実は、
ほかの 安全:リスク資産の『比率』に比べると、
以下、
愚者小路さんがブログ記事の中で、
理論的に、かつ順序立てながら説明してくださっています。
あなたのイメージとは異なるかもしれませんが、
実はリタイア後に、
安全:リスク資産 = 50:50を維持し続けるって、けっこうアグレッシブな管理体制なのです。

以下、愚者小路さんの説明体系に倣います。
あなたの総資産100万円を、
安全:リスク資産 = 10:90でキープしているとしましょう。
つまり、
安全:リスク資産 = 10万円 90万円 です。
リスク資産が半減(-50%)してしまいました。
つまり、
安全:リスク資産 = 10万円 45万円 に・・。
当然、
リ・バランスを行って、
安全:リスク資産 = 10:90 に戻します。
この際、
リスク資産の買い付け額は意外と少なく、わずか「4.5万円」です。
※実際、計算してみてください。
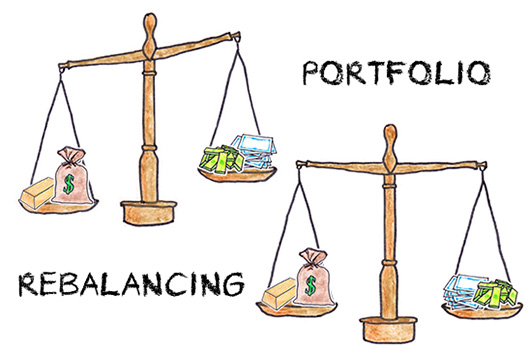
実は、
安全:リスク資産 = 90:10の配分比率の場合も、
リスク資産が半減(-50%)で
安全:リスク資産 = 90:10 にリ・バランスを行う際は、
リスク資産の買い付けは「4.5万円」のみです。
では、
安全:リスク資産 = 50:50の場合はどうなのでしょうか?
(同じく総資産は100万円)
安全:リスク資産 = 50万円 50万円 となります。
ここで暴落が起こり、
リスク資産が半減(-50%)してしまいました!
つまり、
安全:リスク資産 = 50万円 25万円 に・・。
リ・バランスを行って、
安全:リスク資産 = 50:50 に戻します。
この際、
リスク資産の買い付け額は意外と多く、「12.5万円」になります。
※実際、計算してみてください。

結果、
“ファンド価格が大きく下がった年に、
リスク資産を大きく買い増すことになるわけです。”
実はリスク資産が増えた場合でも、
安全:リスク資産の、さまざまな「比率」の中で、
安全:リスク資産 = 50:50 のケースです。
これが意味するものは?
“ファンド価格が大きく上がった年に、
リスク資産を潤沢に売却する(利益確定)ことになります。”
さあ、『原点』に戻ってみましょう。
資産活用期(取り崩し期)においては、
もはや「新規の投資入金」はありません。
(資産の取り崩しを続けながら)どうやって総資産を長持ちさせるのか?

あなたの資産を長持ちさせるためには、
リスク資産の『価格変動』を生かして、
年に1回、
ファンド価格が下がったときは、ファンドを買い増す
ファンド価格が上がったときは、ファンドを一部売却するという『仕組み』を内包させることが重要です。
そのため、わざわざ『リ・バランスをし続ける』わけです。
そのためにわざわざ、
安全:リスク資産=50:50 を維持するわけです。
一見、地味で保守的な資産配分に見えるのですが・・。

愚者小路さんはブログ記事内で、
いみじくも記されています。
リバランス買付量が最大化するのは比率が半々の時
まさにその通りです。
そして、
リバランス売却量が最大化するのも、
安全・リスク資産の比率が半々の時です。
老後の資産管理では、
安全:リスク資産=50:50 の維持こそが、
長い目で見て、資産を枯渇させない有効な手段であると考えます。
カテゴリ:ポートフォリオ運用, リタイアメント・資産の取り崩し

